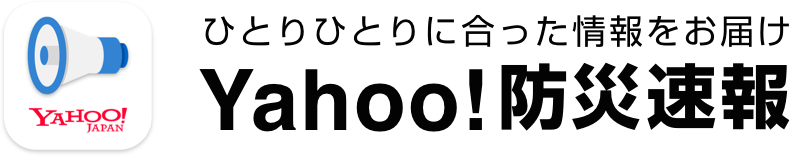災害から命を守る
ヤフーの防災アプリ

防災情報通知
さまざまな防災情報を迅速にプッシュ通知
早め早めの行動判断をサポートします

 現在地と国内3地点まで
現在地と国内3地点まで
設定可能 緊急地震速報など
緊急地震速報など
さまざまな情報に対応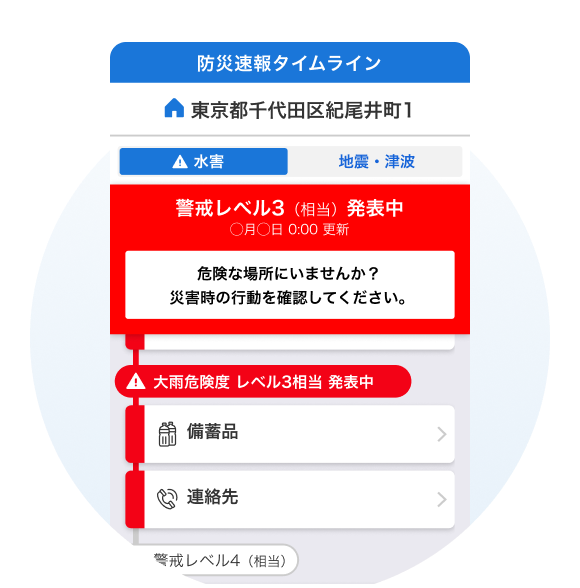 「防災タイムライン」で
「防災タイムライン」で
備えや行動を確認できる
災害マップ
ユーザー同士で状況を共有でき
どんな災害がどこまで迫っているかがわかります

 ユーザーによる
ユーザーによる
状況の共有 ライフラインの
ライフラインの
供給情報 報道メディア・NPO等
報道メディア・NPO等
連携パートナーによる投稿
防災手帳
防災で一番大切な普段の備えから
災害で困ったときに役に立つ情報を幅広く掲載
- 避難場所リスト
- ハザードマップ
- 緊急連絡先
- 防災用品
- 困ったときは